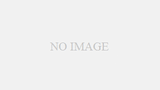サイト売却(サイトM&A)では、デューデリジェンス(DD)と呼ばれる買収前の調査が、取引を安全かつ円滑に進める上で欠かせないプロセスです。
デューデリジェンスでは、サイトのアクセス数や収益など価値を決める重要な数字に誤りや隠れたリスクがないかを徹底的に確認します。
初心者のサイトオーナーにとって専門的な印象があるかもしれませんが、本記事ではデューデリジェンスとは何か、その具体的な流れとチェックポイント、そして売り手側が準備すべき資料について、専門的な内容をできるだけわかりやすく丁寧に解説します。
結論としては、事前に適切な準備を行い誠実に対応することで、買収監査とも呼ばれるデューデリジェンスを安心して乗り切り、サイト売却を成功させることができるでしょう。
デューデリジェンスとは?サイト売却で重要な理由
デューデリジェンス(Due Diligence、買収監査)とは、買収対象となるビジネスや企業の経営状況や数値データを調査・確認することです。
直訳では「当然に実施すべき注意」といわれるように、本来はM&Aや投資において相手の価値やリスクを把握するために行われる調査のことを指します。
サイトM&Aの文脈では、「買い手が買収するサイトに問題がないか事前に確認する作業」と言い換えることができます。
サイト売却においてデューデリジェンスが重要視される理由は、サイトの価値を左右する指標(売上高、アクセス数、利益など)が正確であることを確認し、将来的なリスクを洗い出すためです。
実際、Webサイトの価値は収益やアクセス数、月間利益などで評価されますが、もしこれらの数字に誤りがあれば、後々大きなトラブルに発展しかねません。
そのため、本契約前に買い手によるデューデリジェンスをしっかり行うことが求められます。
特にサイトM&Aでは、通常の企業M&Aの調査項目に加えて、収益性の裏付けやSEO手法、法的リスクの有無などWeb特有のポイントも重点的にチェックされます。
なお、デューデリジェンスは法律で義務付けられた手続きではなく、あくまで取引を安全に進めるための自主的な調査です。
とはいえ、どんな場合でもデューデリジェンスは基本的に必要不可欠であり、このプロセスを怠ると適正なサイト査定やスムーズな譲渡が難しくなります。
買い手・売り手双方にとって安心して取引を完了するためにも、デューデリジェンスへの十分な理解と準備が重要です。
サイト売却におけるデューデリジェンスの流れ
サイトM&A全体の手順の中で、デューデリジェンスは「基本合意(仮契約)の締結後~最終契約前」の段階に位置します。
以下では、サイト売却時におけるデューデリジェンスの具体的な進め方を順を追って解説します。
1. 基本合意と秘密保持契約の締結(準備段階)
サイト売却の交渉が進み、買い手から大筋の条件提示を受けたら、まず秘密保持契約(NDA)を締結します。
デューデリジェンスでは機密性の高いデータや資料を開示するため、NDAを交わして情報漏洩を防いだ上で調査を開始するのが安心です。
次に、買い手・売り手の間で基本合意書(LOI)を取り交わします。
基本合意書には、概算の譲渡価格や主要な取引条件、今後のスケジュールなどが記載され、本格的なデューデリジェンスに進むための道筋となるものです。
一般的なM&Aでは基本合意書締結後、買い手は一定期間他の交渉を控える独占交渉権を得て、集中的にデューデリジェンスを行います。
準備段階では、買い手側でデューデリジェンスの範囲やスケジュールをあらかじめ計画します。
サイトM&Aの場合、調査範囲は比較的限定的ですが、買収対象によって重点項目が異なるため、「どの分野をどこまで調べるか」を事前に合意しておくとよいでしょう。
調査にかける期間はサイトの規模や内容により様々ですが、小規模サイトなら2週間程度で完了するケースも多く、一方で規模が大きい場合や調査項目が多い場合は1~2ヶ月要することもあります。
あらかじめ双方でデューデリジェンス期間を定め、スケジュールに組み込んでおきましょう。
2. 買い手からの資料請求と情報開示(デューデリジェンス開始)
基本合意後、買い手側はデューデリジェンスの具体的なチェックリストを作成し、売り手に対して必要な資料・情報の提供を依頼します。
この資料請求リストには、財務データやアクセス解析データ、契約書類など、調査に必要な項目が網羅されます。
買い手は小出しに情報を求めるのではなく、一括でリストアップして依頼するのが一般的であり、売り手側もできる限り早めに必要資料を揃えて提供することが望ましいです。
売り手が提供すべき情報の詳細は後述しますが、例えばサイトのGoogleアナリティクスの閲覧権限を共有したり、過去の収益をまとめたエクセル資料を提出したりします。
また収益エビデンスとして、広告収入やアフィリエイト収入の管理画面スクリーンショット、ECサイトなら管理画面の売上データや通帳の該当入金箇所コピーなども求められる場合があります。
契約関係では、外注スタッフとの契約書や主要な取引先との契約書類があればそれも開示します。これらの資料はオンライン上のデータルーム(クラウドストレージなど)にまとめてアップロードするか、仲介担当者経由で手渡し・送付する形で提供されます。
情報開示にあたって大切なのは、正確かつ誠実にデータを開示することです。
不利な情報だからと隠したり数字をごまかしたりすると、後の調査で発覚した際に信用を失い、取引破談や価格交渉の不利につながりかねません。
多少マイナス要素であっても先に共有し、買い手の理解を得ておくことが円滑なサイト売却につながります。
3. 資料の精査・分析と質疑応答(デューデリジェンス期間中)
デューデリジェンス期間中、買い手は提供された資料をもとに綿密な分析とチェックを行います。
買い手(または買い手が依頼した専門チーム)は、提示された数値が正しいか裏付けを取り、不明点があれば売り手に質問を投げかけます。
例えば、売上やアクセス数の検証では、売り手から提出された収支表の数値とGoogleアナリティクス等の実データを照合し、不整合がないか確認します。
過去のトレンドから見て異常な数値の変動があれば、その理由(季節要因や一時的キャンペーン効果など)をヒアリングするでしょう。
また、SEOの状況について専門ツールで分析し、急激なアクセス増減や不自然な被リンクがないかといったサイト特有のチェックも行います。
調査の過程では、質疑応答(Q&A)が何度か発生します。
買い手は疑問点を整理し、質問リストを文書で売り手に送付して回答を求める形が一般的です。
対面で直接ヒアリングが行われる場合もありますが、日程調整の手間から書面でのやりとりが中心となるケースが多く、質問事項が多い場合はExcelやドキュメントで質問と回答を一覧化する方法が用いられます。
売り手側はこれらの質問に対し、できるだけ早く正確な回答や追加資料を提示しましょう。
場合によっては追加で資料提供を再依頼されることもあります。
例えば、「直近○ヶ月の詳細な月次PLも見たい」「○月のアクセス急増の原因分析資料が欲しい」といったリクエストに応じる形です。
依頼が遅れると全体スケジュールに影響するため、迅速な対応が肝心です。
売り手にとって、デューデリジェンスで細かくチェックされるのは「粗探しをされているようだ」と不安に感じるかもしれません。
しかしこれは買い手が安心して適正価格で購入するために必要なプロセスであり、問題点を指摘されることを恐れず誠実な姿勢で対応することが大切です。
質問に対して曖昧な返答をしたり、答えに詰まって沈黙したりすると、買い手の不信感につながります。どんな質問にも冷静に客観的なデータや事実に基づいて回答し、必要に応じて専門家(会計士や弁護士、仲介担当者)の力も借りながら丁寧に対処しましょう。
4. 結果の報告・共有と最終契約交渉(クロージング前)
デューデリジェンスが一通り完了すると、買い手は調査結果を踏まえて最終的な購入判断と条件の検討を行います。
専門チームに依頼していた場合は、ここでデューデリジェンス報告書が買い手に提出されます。
買い手は報告内容を精査し、当初想定していた事業価値とのギャップやリスクの有無を確認します。
もし大きな問題が見つからなければ、予定どおり最終契約(譲渡契約)の締結に進みます。
基本合意時の提示条件に沿って契約書を作成し、売買価格や譲渡資産、引き継ぎ条件などを最終確定させます。
一方、デューデリジェンスで当初予見していなかった課題が判明した場合、買い手はその内容に応じて対応を検討します。
例えば、過去の業績が売り手主張より下振れしていた場合や、一部コンテンツに著作権上のリスクが見つかった場合などです。
問題が致命的で事業価値に重大な影響を及ぼす場合、最悪ケースでは取引中止(基本合意の撤回)という判断もあり得ます。
そこまでではなく改善可能な範囲であれば、価格の減額交渉や契約条項への保証・補償の盛り込みなどでリスクヘッジを図り、取引を継続する方向で調整します。
たとえば「指摘の不備について売り手が○○までに是正する」「想定より利益が低かった分、売却額を△△万円減額する」といった取り決めを最終契約書に反映させます。
最終契約においては、競業避止(ノンコンペ)条項の設定も重要です。
これは、サイト譲渡後に売り手がすぐ類似のサイトを立ち上げて競合しないよう制限する条項で、ほとんどの場合契約に盛り込まれます。
こうした細部の条件まで双方合意できれば契約書に署名押印し、クロージング(譲渡実行)へと進みます。
クロージングでは代金支払いと同時に、サイトのドメイン移管やサーバー・コンテンツデータの引き渡し、関連アカウントの移行などを行い、買い手が無事サイト運営を引き継げる状態にします。
これでデューデリジェンスを含む一連のサイトM&Aプロセスが完了です。
デューデリジェンスでチェックされる主なポイント
デューデリジェンスでは、多角的な観点からサイトの価値とリスクを調査します。
具体的には以下のポイントが買収前のチェック項目として重視されます。
収益・財務状況の確認
過去の売上高や月間利益など収益性が適切かを精査します。水増しや不正な計上がないか、帳簿の数字と実際の入金記録が合っているかを確認します。
特にWebサイトの価値評価では売上や利益が重要なため、GoogleアドセンスやASP報酬の明細、通販サイトであれば売上管理画面や銀行入金履歴などを突き合わせ、収益データの裏付けを取ります。
また、一時的なキャンペーン等で発生した特殊要因の除外(いわゆる正常収益力の把握)も行い、持続的な収益力を見極めます。
アクセス数・集客状況の確認
サイトのトラフィック(訪問者数、PV数)が公称通りかを確認します。
具体的には、Googleアナリティクスやサーチコンソールのデータを開示して、検索キーワードの順位、月間PV・UU、直帰率、ユーザーの地域分布、成長率など様々な指標をチェックします。
不自然なトラフィック(ボット流入や買収したアクセスなど)がないか、主要流入経路が特定の広告に依存しすぎていないか、といった点も評価されます。
また、複数年運営しているサイトであればアクセス推移のトレンドを確認し、近年伸びているのか下降傾向にあるのかといった成長性も見られます。
SEO・ドメイン関連の健全性
Googleのガイドラインに違反するようなブラックハットSEO(例えば不自然な被リンク集めや隠しテキストなど)で一時的に検索順位を上げていないか、過去に検索ペナルティを受けていないか、
ドメインの被リンクプロファイルにスパム的なものが混在していないか等を専門ツールで調査します。
仮に検索順位が高く多くの集客を得ていても、その状態が検索アルゴリズム更新で大きく変動するリスクがないかを見極めるわけです。
また、ドメインが適切に管理されているか(有効期限切れ間近でないか、移管ロックは解除可能か)など技術的・管理面の確認も行います。
コンテンツの品質と権利関係
サイト上のコンテンツ内容が法令や権利上問題ないかも調査されます。具体的には、掲載記事や画像・動画などに盗用・転載がないか(他サイトからのコピペコンテンツではないか)を確認します。
画像素材や記事内容が第三者の著作権・肖像権を侵害していないかも重要なチェックポイントです。
例えば商品紹介サイトであればメーカーの公式画像を無断使用していないか、ブログ記事で引用の範囲を超える転載をしていないか等を見ます。
不適切なコンテンツ(法律に触れるような表現や公序良俗に反する内容)が含まれていないかも確認されます。
これら法務デューデリジェンスに該当する部分で問題が放置されていると、買収後に訴訟リスクやサービス停止といった事態につながりかねないため、細心の注意を払ってチェックされます。
ユーザー関連のリスク
サイト利用者や取引先との間で潜在的なトラブルがないかも調査対象です。
例えば、サイトがユーザー向けサービスを提供している場合は利用規約やプライバシーポリシーが整備されているか、過去に大規模なクレームや個人情報漏洩事故がなかったかを確認します。
ECサイトであれば顧客からの返品・返金トラブルの有無、会員情報の適法な管理状況なども見られるでしょう。
コミュニティサイトであれば炎上履歴や風評被害が残っていないか、投稿監視体制があるかといった点もチェックされます。
要するに、将来損害賠償責任を負うようなリスクが潜んでいないかを洗い出す工程です。
運営体制・人材面
サイト運営に関わる人の要素も確認します。
基本的にサイトM&Aでは人員ごと譲渡されることは少ないですが、外注スタッフや関係者がいる場合、その状況を把握します。
例えば「記事作成を特定のライターに外注しているが、譲渡後も継続可能か」「システム開発を委託している場合、その契約はどうなるか」等です。
必要に応じて外注先との契約書を確認し、著作権の帰属や契約継続条件をチェックします。
また、サイト運営者個人のスキルに大きく依存していないか(引き継ぎ後に買い手が運営を回せるか)といった観点も見られます。
従業員を雇用しているケースでは従業員リストや雇用条件を確認し、買収による雇用契約引き継ぎや退職金債務などの論点も調査するでしょう。
小規模サイトではあまり該当しませんが、人的リソース・ノウハウの引き継ぎもデューデリジェンスの重要テーマになり得ます。
以上のように、デューデリジェンスではサイトの財務・ビジネス面から法務・技術面まで幅広くチェックが行われます。
買い手はこれら情報を総合して「このサイトを予定価格で買って問題ないか」「将来の成長性やリスク許容の判断は適切か」を見定めるのです。
売り手としても、どの点を見られるか把握しておくことで事前準備がしやすくなります。
売り手側が準備すべき資料・情報リスト
デューデリジェンスをスムーズに進めるには、売り手側で事前に必要資料を整理しておくことが効果的です。以下に、サイト売却時によく求められる資料や情報の例を挙げます。
サイト概要資料
サイトの事業内容や収益モデル、主要コンテンツ、ユーザー属性などをまとめた資料。会社組織で運営している場合は会社案内やパンフレットに相当するもの。
サイトの沿革(開設時期やこれまでの運営体制)、競合優位性、市場ポジションなども簡潔に説明できると良いでしょう。
トラフィック関連データ
GoogleアナリティクスやSearch Consoleのデータは必須です。
閲覧権限を付与するか、主要なレポートをPDF等で提出します。
具体的には直近数年(または数ヶ月)の月次PV・UU、流入経路の内訳(オーガニック検索、SNS、広告etc)、検索上位キーワードとその順位、直帰率や訪問時間などのエンゲージメント指標が分かる資料が望ましいです。
あわせて、アクセス傾向を示すグラフや成長率の数値も整理しておきます。
財務・収益に関する資料
サイトから得られる収益と費用の情報一式です。
収益面では、過去12ヶ月~3年分程度の月次売上高・利益(サイト単体の損益)をまとめた表を用意します。
法人の場合は直近3期分の決算書・確定申告書(貸借対照表・損益計算書など)と、当期途中までの月次試算表が求められます。
個人事業の場合でも、可能なら簡易財務諸表や青色申告決算書を準備すると説得力が増します。
エビデンスとして、収益源ごとの裏付け資料も必要です。
例として、GoogleアドセンスやAmazonアソシエイト等広告収入は管理画面のレポートや振込履歴のスクリーンショット、ECサイトなら各月の売上レポートと銀行口座の入金記録、サブスクリプションサービスなら会員数・課金額がわかる管理画面のキャプチャなどです。
費用面では、サーバー代・ドメイン更新費・外注費など主な経費項目と年間合計額をまとめておきます。
人件費や販促費を計上している場合はその明細も示すと、買い手が実質的な利益水準を把握しやすくなります。
契約・権利関係の書類
サイト運営に関連する各種契約書類も整理します。
外注先との契約書(ライターや開発者への業務委託契約書など)があれば用意し、著作権譲渡の有無や守秘義務の範囲を確認できるようにします。
主要な取引先(仕入先やスポンサー等)がいる場合、その基本契約書や覚書も対象です。
また、サイト上で提供しているサービスに関する利用規約・プライバシーポリシーの最新版、ユーザーから同意を得ているならそのエビデンス(サイト上に掲示しているURLなど)も示します。
知的財産では、サイト名やロゴの商標登録証、独自開発システムが特許出願している場合その書類、使用中の画像や文章で購入した素材があればそのライセンス証明書などが挙げられます。
サイトに必要な許認可(例えば古物商許可や特定商取引法に基づく表示)がある業種では、該当する許可証や届出書の写しも忘れずに準備します。
ドメイン・SNSアカウント等の情報
譲渡対象となるドメインの登録情報(レジストラや有効期限、移管コードの取得方法)を整理します。
SNS連携している場合はSNSアカウントの概要(フォロワー数やエンゲージメント)や引き継ぎ方法のメモも用意します。
アプリやシステム連携があるサイトでは、APIキーや開発者アカウントの譲渡可否も確認事項です。
その他サイト固有の情報
上記以外にも、サイトの種類によって固有の資料が求められます。
たとえばコミュニティサイトであればユーザー数やアクティブ率、有料会員数などのデータ、ECサイトで在庫や商品リスト、仕入先リスト、SaaSサービスなら主要顧客リストや解約率などが該当するでしょう。
また将来の事業計画書があれば任意提出します。
必須ではありませんが、買い手にポジティブな印象を与える資料として用意するケースもあります。
これらの資料は、サイト売却を検討する段階から早めに準備・整理しておくことをおすすめします。
そうすることで、いざ買い手が現れてから慌てて作成する手間が省け、また自サイトの強み・弱みを客観的に見直す機会にもなります。
デューデリジェンス中に追加要求が出てもすぐ対応できるよう、日頃からデータは蓄積しておきましょう。
特にアクセス解析や収益の証拠は後から遡って取得できない場合もあるため(例えば過去のアナリティクスデータ保持期間設定など)、定期的にエクスポートしておくと安心です。
初心者の売り手が安心してデューデリジェンスを乗り切るために
デューデリジェンスの流れと必要書類が把握できれば、未知のプロセスへの不安も軽減されるでしょう。
最後に、初心者のサイトオーナーがデューデリジェンスを安心して乗り切るためのポイントをまとめます。
誠実で迅速な対応
調査を受ける側として最も大切なのは、嘘をつかず正直に情報提供することです。
隠し事をせずオープンに向き合うことで、買い手からの信頼も得られます。
また質問や追加依頼にはできるだけ早く回答し、レスポンスの良さを示しましょう。対応が遅れると不安を与えかねません。
社内調整に時間がかかる場合も、中間報告を入れるなど丁寧なコミュニケーションを心がけてください。
ネガティブ情報も先出しする
過去にアクセス減少の時期があった、一部コンテンツの削除を行った等、マイナスとなりうる事柄も先に自己申告したほうが結果的に信頼度は増します。
買い手は問題点も含めてサイトの価値を判断しますので、「指摘されなかったから言わないでおこう」ではなく、自ら開示する姿勢が重要です。
もちろん聞かれなかったことまで過剰に伝える必要はありませんが、核心に関わるリスクは事前共有が鉄則です。
専門家や仲介サービスの活用
デューデリジェンスの対応に不安がある場合は、サイトM&Aの専門家に相談・依頼するのも一つの手です。
経験豊富な仲介会社であれば、資料の取り揃え方や開示範囲のアドバイス、買い手との質疑応答の仲介まで手厚くサポートしてくれます。
実際、サーバー移転や著作権処理、交渉ごとなど専門知識が必要な場面は少なくないため、第三者のサポートがあると心強いでしょう。
もちろん信頼できる会社を見極めて依頼することが前提ですが、初めてのサイト売買ならプロの力を借りる価値は高いです。

こうしたポイントを押さえて準備すれば、初心者の売り手であっても落ち着いてデューデリジェンスに臨めるはずです。
買い手との情報共有を通じてお互いの理解が深まり、取引後のトラブルを未然に防ぐ保険にもなるのがデューデリジェンスです。
売却側にとっては自サイトの棚卸しにもなりますので、このプロセスを前向きに捉えて取り組みましょう。
まとめ:デューデリジェンスを経て安心・安全なサイト売却を
デューデリジェンスの流れとポイントを総合すると、サイト売却におけるデューデリジェンスは「買い手が安心してサイトを引き継ぐための最終確認プロセス」と言えます。
初心者のサイトオーナーにとって専門的でプレッシャーを感じる場面かもしれませんが、本記事で解説したように適切な準備と誠実な対応があれば過度に恐れる必要はありません。
デューデリジェンスをしっかりと乗り越えることで、サイトの本当の価値が買い手にも伝わり、結果的に満足度の高いサイトM&Aを実現できるでしょう。
サイト売買は決して一人で抱え込む必要はありません。M&Aクラブのような専門プラットフォームを活用すれば、サイト査定の段階から契約交渉、デューデリジェンス対応、譲渡手続きに至るまで一貫したサポートを受けることができます。
実際、M&Aクラブ(MAクラブ)では通常のM&A仲介で発生する着手金・固定手数料が一切不要で、売却成立時のシステム手数料10%のみと非常にリーズナブルです。さらに取引金額はエスクロー(一時預かり)方式で安全に管理されるため、初めての方でも安心してサイト売却に臨めます。
デューデリジェンスも含め何か不明点があれば専門スタッフがフォローしてくれるので、心強いパートナーとなるでしょう。
最後に、デューデリジェンスはサイト売却の重要ステップですが、これをクリアすればあとは新しいオーナーへサイトをバトンタッチするだけです。
万全の準備で臨み、ぜひ納得のいく形であなたのサイトを次のステージへ託してください。
専門家のサポートで安心のサイト売却を
デューデリジェンスの準備や対応に不安がある方は、
サイト売買の実績豊富な「M&Aクラブ」にご相談ください。
査定から契約・引き継ぎまで、初めての売却でもしっかりサポートします。